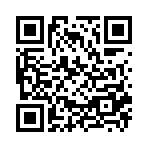2017年01月29日
砲兵に支援してもらおう1
こんばんは、センター試験が無事終了し、現在一般に向け、勉強をしていないチベスナです。
今回は個人的にめっちゃ気になっていた、FO(forward observer)の砲撃支援要請方法について適当に調べたので、
適当にまとめておきます。
編成とか役割とか
まず、火力支援チーム、砲兵部隊についての説明をしておきます。
旅団や師団に所属しているあたりに付属している砲兵連隊って奴です
その中隊内の役割分担みたいな奴についてまとめました。
こんな感じ、詳しく説明して行きますね
FSO fire support officer 中隊で一人選抜され、FOの指揮や火力支援の計画実行などを行います
FSS fire support sergeant FSOの行動を手助けし、また、FSOが不在の時はFSSがFSOの仕事を引き継ぐ事ができます。
FO Forward observer FOの仕事はコンパスや地図を使用し、砲兵部隊の目となる事です、FOからFDCに無線を使用し砲撃目標を知らせ、砲撃の判定、評価を行います。
歩兵小隊に配属されたりOP(observe Post)に配置されたりします、配置はFSOが決定します。
FSP fire support specialist 砲の整備とかFSSの雑用、FOの仕事もしたりします
RTO 無線手 FIST(fire support team)に配属され無線手を行う場合と、FOと行動を共にして無線業務を行う場合も有り、FOとしても行動する場合があります。
こんな感じ。間違ってたら許して。それより下の装備は中隊に配備される装備になります、M113を改造した砲兵用の観測車とか無線機、レーザ測距機などです。
FOの標的指示方法
FOによる標的の指示方法と言えば、皆さんは座標を使った「グリットAH100132…」みたいな交信方法をイメージすると思います、
ですが、基本的にはFOが使用する標的の指示方法は3つ存在しており。
「極座標を使用した指示」
「座標を使用した指示」
「事前に打ち合わせを行った場所から距離を使用した方法」
が有ります。
順にざっと紹介して行きましょう。(紹介文はmilという角度単位について、既に既習済みと考えて書いて有ります。)
極座標を使用した方法
極座標と聞いてピンと来る人は理系です、たぶん高校では数三をやってます。
極座標と言うのはX-Y平面上の点を角度と距離で表す方法で、簡単に説明すると数1や中学数学で行った関数(X,Y)が(1,1)で有った場合、X軸に+1、Y軸に+1動いた点を表します。
こんな感じ
これを原点Oから角度と点(1,1)から原点Oまでの距離で位置を表します、この場合は45度の線が長さ√2の距離で表せるので(1/4π,√2)と表せます

これで、原点O(FOの位置)から角度(ミルで示しますので、Y軸上が0000となります)と双眼鏡等で測距した距離を使用し、砲撃目標をFDCに伝える事ができます。
例(真東の距離、1340mあたりに目標がある場合)
OT direction1600 distance1300と表記します、角度は4桁で表記し、たとえミル角度が10でも
0010と言いましょう、聞き間違えを減らします、また、距離は100m単位です。また、目標とFOとの高度に大きな差がある場合(35m以上)は垂直方向の指示もします。
この方法では地図を使用しないと言う利点が有り、はじめにグリッド座標を振らなくていいですが、FOの正確な位置をFDCに伝える必要があります、
FOがFDCに報告しなくてはならない事は
自分の位置(OPに固定されている場合はコールサインで問題なし)
ミル角度(10ミル以下四捨五入)
距離(100メートル以下四捨五入)
標高差±35を超えた場合は標高を5m刻み
になります
グリッド座標を使用した方法
これは皆さんがよくイメージする位置の指示方法なのではないでしょうか?
こちらの指示方法を使用した場合、FOはFDCに自身の居場所を教えなくて良い利点があります。
FOは通常100m四方に区切られた地図の中から目標の位置を探し、6桁の数字でグリッドをFDCに教えます
グリッドの発見方法はFOが地図上に極座標を使用して自分の位置から標的の距離と角度を確認し、標的が居る位置のグリッドを見つけます、
また、8桁のグリッドを使用する場合も有り、これは、10m四方を指示できるため、精度が高くなります。基本的に高度は教えなくて問題ありません。FDCも同じ地図持ってるので、勝手に合わせてくれます。
FOがFDCに伝えるべき事は
グリッド
標高(無くてもいい)
を報告しなくてはなりません
事前に打ち合わせを行った場所から距離を使用した方法
これは一番めんどくさいかもしれないです、
FDCとFOの間で取り決めを行い、FOは砲撃目標を指示するための基準点を1つ以上決める事ができます。
そこを基準にした方法です。地図を使わなくても良いことになってますが、使った方が正確だと思います、
また、この方法をとる場合、FOの位置はFDCに連絡しなくても問題ありません。
簡単に分かるような図を制作しました。

まず、標的を発見した場合、基準点との角度の差(ミル)を使用し、Wを出します
計算方法はW=R×mil/1000 です
この図は簡単にするため、基準点をFOから見てちょうど真北に位置するようにしました、
そして、OTline(observer target)の線を引いたところを示すミル角度から基準点ミル角度を引きます。
この場合、0100-0000なので、0100ミルFOから基準点を見て、標的との角度の差があると言うことが分かります。
次に、赤い線の距離Wを求めます。
これは、まず、FOの基準点までの距離Rを測ります、この図ではわかりやすいように1000mとしました。
この場合、W=1000×100/1000と言う計算式が成り立ち、W=100と出てきます。(これは10の位を四捨五入します)
よって、この標的は基準点から右に100mずれた線のOTlineのT'にぶつかります、そこから、標的は±何メートルかを100メートル単位で設定します。この方法は基準点からTOlineが600ミル以上離れていた場合は誤差が大きくなるため、使用できません。
そしてFOはFDCに無線で標的の位置を知らせる場合は、
FO自身から見たOTlineのミル角度(図では0100)
スライドする方向(左右)と距離(10m単位)
TOlineから見たT’と標的の距離の差(±100m単位)
基準点と比べた標高差(±35m以上の場合、5m刻みで)
をFDCに報告します。
やる気が有れば続き書きますね
今回は個人的にめっちゃ気になっていた、FO(forward observer)の砲撃支援要請方法について適当に調べたので、
適当にまとめておきます。
編成とか役割とか
まず、火力支援チーム、砲兵部隊についての説明をしておきます。
旅団や師団に所属しているあたりに付属している砲兵連隊って奴です
その中隊内の役割分担みたいな奴についてまとめました。
| 機械化歩兵 | 機甲 | 歩兵 | 軽師団 | 空挺 | エアアサルト | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSO (LT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FSS (SSG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FO (SGT) | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| FSP (SP4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RTO (PFC) | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ハンビー | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| AN/VRC-88 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| AN/VRC-91 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| AN/PRC-119 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| DMD | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| FIST DMD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AISTV or APC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/VLLD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
こんな感じ、詳しく説明して行きますね
FSO fire support officer 中隊で一人選抜され、FOの指揮や火力支援の計画実行などを行います
FSS fire support sergeant FSOの行動を手助けし、また、FSOが不在の時はFSSがFSOの仕事を引き継ぐ事ができます。
FO Forward observer FOの仕事はコンパスや地図を使用し、砲兵部隊の目となる事です、FOからFDCに無線を使用し砲撃目標を知らせ、砲撃の判定、評価を行います。
歩兵小隊に配属されたりOP(observe Post)に配置されたりします、配置はFSOが決定します。
FSP fire support specialist 砲の整備とかFSSの雑用、FOの仕事もしたりします
RTO 無線手 FIST(fire support team)に配属され無線手を行う場合と、FOと行動を共にして無線業務を行う場合も有り、FOとしても行動する場合があります。
こんな感じ。間違ってたら許して。それより下の装備は中隊に配備される装備になります、M113を改造した砲兵用の観測車とか無線機、レーザ測距機などです。
FOの標的指示方法
FOによる標的の指示方法と言えば、皆さんは座標を使った「グリットAH100132…」みたいな交信方法をイメージすると思います、
ですが、基本的にはFOが使用する標的の指示方法は3つ存在しており。
「極座標を使用した指示」
「座標を使用した指示」
「事前に打ち合わせを行った場所から距離を使用した方法」
が有ります。
順にざっと紹介して行きましょう。(紹介文はmilという角度単位について、既に既習済みと考えて書いて有ります。)
極座標を使用した方法
極座標と聞いてピンと来る人は理系です、たぶん高校では数三をやってます。
極座標と言うのはX-Y平面上の点を角度と距離で表す方法で、簡単に説明すると数1や中学数学で行った関数(X,Y)が(1,1)で有った場合、X軸に+1、Y軸に+1動いた点を表します。
こんな感じ

これを原点Oから角度と点(1,1)から原点Oまでの距離で位置を表します、この場合は45度の線が長さ√2の距離で表せるので(1/4π,√2)と表せます

これで、原点O(FOの位置)から角度(ミルで示しますので、Y軸上が0000となります)と双眼鏡等で測距した距離を使用し、砲撃目標をFDCに伝える事ができます。
例(真東の距離、1340mあたりに目標がある場合)
OT direction1600 distance1300と表記します、角度は4桁で表記し、たとえミル角度が10でも
0010と言いましょう、聞き間違えを減らします、また、距離は100m単位です。また、目標とFOとの高度に大きな差がある場合(35m以上)は垂直方向の指示もします。
この方法では地図を使用しないと言う利点が有り、はじめにグリッド座標を振らなくていいですが、FOの正確な位置をFDCに伝える必要があります、
FOがFDCに報告しなくてはならない事は
自分の位置(OPに固定されている場合はコールサインで問題なし)
ミル角度(10ミル以下四捨五入)
距離(100メートル以下四捨五入)
標高差±35を超えた場合は標高を5m刻み
になります
グリッド座標を使用した方法
これは皆さんがよくイメージする位置の指示方法なのではないでしょうか?
こちらの指示方法を使用した場合、FOはFDCに自身の居場所を教えなくて良い利点があります。
FOは通常100m四方に区切られた地図の中から目標の位置を探し、6桁の数字でグリッドをFDCに教えます
グリッドの発見方法はFOが地図上に極座標を使用して自分の位置から標的の距離と角度を確認し、標的が居る位置のグリッドを見つけます、
また、8桁のグリッドを使用する場合も有り、これは、10m四方を指示できるため、精度が高くなります。基本的に高度は教えなくて問題ありません。FDCも同じ地図持ってるので、勝手に合わせてくれます。
FOがFDCに伝えるべき事は
グリッド
標高(無くてもいい)
を報告しなくてはなりません
事前に打ち合わせを行った場所から距離を使用した方法
これは一番めんどくさいかもしれないです、
FDCとFOの間で取り決めを行い、FOは砲撃目標を指示するための基準点を1つ以上決める事ができます。
そこを基準にした方法です。地図を使わなくても良いことになってますが、使った方が正確だと思います、
また、この方法をとる場合、FOの位置はFDCに連絡しなくても問題ありません。
簡単に分かるような図を制作しました。

まず、標的を発見した場合、基準点との角度の差(ミル)を使用し、Wを出します
計算方法はW=R×mil/1000 です
この図は簡単にするため、基準点をFOから見てちょうど真北に位置するようにしました、
そして、OTline(observer target)の線を引いたところを示すミル角度から基準点ミル角度を引きます。
この場合、0100-0000なので、0100ミルFOから基準点を見て、標的との角度の差があると言うことが分かります。
次に、赤い線の距離Wを求めます。
これは、まず、FOの基準点までの距離Rを測ります、この図ではわかりやすいように1000mとしました。
この場合、W=1000×100/1000と言う計算式が成り立ち、W=100と出てきます。(これは10の位を四捨五入します)
よって、この標的は基準点から右に100mずれた線のOTlineのT'にぶつかります、そこから、標的は±何メートルかを100メートル単位で設定します。この方法は基準点からTOlineが600ミル以上離れていた場合は誤差が大きくなるため、使用できません。
そしてFOはFDCに無線で標的の位置を知らせる場合は、
FO自身から見たOTlineのミル角度(図では0100)
スライドする方向(左右)と距離(10m単位)
TOlineから見たT’と標的の距離の差(±100m単位)
基準点と比べた標高差(±35m以上の場合、5m刻みで)
をFDCに報告します。
やる気が有れば続き書きますね